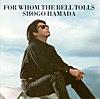浜田省吾ヒストリー⑫ アルバム「誰がために鐘は鳴る」

浜田省吾さんの歴史を振り返るコーナー。12回目は…。
アルバム「誰がために鐘は鳴る」
前回のアルバム「FATHER'S SON」は、父親の死を機に
もう誰かの子供ではなくなってしまったんだと感じて
自分のルーツとは何か?ということも交えて
強く影響を受けたアメリカのことや、アメリカと日本の関係について
省吾さんが思ったことを曲に込めたアルバムになりました。
そして、そのアルバムを引っ提げてコンサートツアーを終えた時に
昭和という時代が終わったということもあり
公私共に、省吾さんの中で1つの区切りになったアルバムでもありました。

その後、2年3ヵ月ぶりに
次なるアルバム「誰がために鐘は鳴る」を発売するわけですが。
それまでの間に省吾さんは
一区切りついたことが影響してなのか?
燃え尽き症候群のように
アラフォーになると男性でも発症する更年期障害の症状が出てしまい
軽いウツ状態に陥ってしまったんです。
その時の省吾さんは、何もヤル気が起きず、全ての事が空虚に感じられ
曲作りやライブツアーなど開催する気になれない状態になっていました。
このまま日本に居ても、そこから抜け出せないと感じた省吾さんは
アメリカやカナダに行くことにしたんです。
そうして休養期間中に、もう一度自分のやりたかった音楽とは何か?
っということを見つめ直して出来た作品が、このアルバムになりました。
そのためか?
聞いていると、パーソナルな部分を
深く描いた作品が多かったように感じられてきます。
同時に省吾さんが自分自身を救済するアルバムにも思えてきました。
アルバムのタイトルからも、それが伺える気がします。
(ヘミングウェイの小説のタイトルでもあり
その中に出てくる詩人ジョン・ダンの詩の一節でもありますよね)
中でも、その時の省吾さんの気持ちが色濃く表れているのが
「MY OLD 50'S GUITAR」と「夏の終わり」と「詩人の鐘」でした。
「MY OLD 50'S GUITAR」
この曲は、ギターを弾くことで救われた男のことを歌っているんですけれど
ヘミングウェイが猟銃で自殺したというイメージも重なっているようでした。
自分を追い込んでしまう男を描いていますが
そういった状況下に置かれた人間でも
「自分自身で自分を救済できるものが、人それぞれにあるんだよ
それは例えばギターだったり、例えばスポーツであったり
その人が気持ちが注げる物があれば救われるんだ」
っという省吾さんの想いも裏に込められています。
40回目の誕生日に自分の頭を撃ち抜く奴は
あまりに一途な理想と望みを描き続けた そんな男さ
Darlin' 俺を強く抱きしめ繋ぎ止めてくれ
何ひとつ リアルに感じられない
My old guitar 荒んだ心 鎮めてくれ
Emptinesss まるでマイナーブルース
続くよ 永遠に
愛が全ての扉 開けてくれると信じていた少年の日々
穏やかな幸せ あまりに脆くて強い男を演じてきた
Darlin' 俺は臆病風に吹かれてるだけなのか?
それとも見なくてもいい 闇を見たのか?
My old guitar 歪んだ苦痛 麻痺させてくれ
Loneliness まるでマイナーブルース
続くよ 永遠に
「夏の終わり」
この曲は、聞いた瞬間、省吾さんはもう引退してしまうんじゃないか?
っと心配になってしまった曲でした。
実際に、休養中にこんな風に思ってしまったんでしょうね。
心が憔悴しきってしまったようで
ギリギリのところまでいってしまった時の心情が描かれていました。
「もう誰の心も引き裂くことなんてない
この車もギターも売り払い海辺の町
潮風と波の音を枕に1人暮らそう」
「愛してくれた人 打ちのめす程傷つけた
汚れた悲しいメロディー 身を切るように繰り返す
拍手とスポットライトと報われぬ涙の陰で」
「もう誰の心も引き裂くことなんてない
手に入れたものみんな失ったって構わない
残された僅かな時 静かに1人暮らそう」
この曲について、省吾さんは↓こんな風に語っています。
去年の春くらいかな?
今の自分はどうなのかよくわからない。
本を読んでも音楽を聞いても、何もかもが白々としていて
冷え冷えとしてしまっているっていう時期があったんです。
人の作ったものが全て虚しく思える。
今でもそれは、ちょっとあるんですけどね。
唯一くつろげる、信じられるのが、空を流れている雲だったり、海だったり、水だったり、緑だったり。
人工的なモノを見ると吐き気がする時があったんです。
極端な時は、本当に何もかもイヤになるっていう、そういう瞬間が続いて、危ないっという感じで。
だから、このアルバムなんか、出来る気が全くしなかったんです。
ツアーにしても、もう1年もやってないんだから、みんなもやろうよって言って、準備はするんだけどヤル気がしないとか
結局これも延びたんですけどね。
今思えば、ものが出来なかったりするのは、コップにずっと水を注いでいる状態で、溢れるまでは注いでも注いでも出てこないというのに似ている。
でも、やっぱり音楽が好きで歌を作ることが好きでっていう部分は、絶対的なものとして自分の中にあると信じているんですね。
こういうのは絶対一時的なもので、やっているうちに、そういうのが戻ってくるんじゃないかと思った。
だからツアーをやろうと思ったのね。
「浜田省吾事典」より
「詩人の鐘」
この曲は、当時の社会を風刺している曲でもあるんですけれど
混沌としていて先が見えない悪夢なような社会の中でも
自分達を救済してくれるために鐘や警笛が鳴っているから
不安ばかり募らせて嘆かないでいいんだよ
っということを歌っている曲になっていました。
省吾さん自身が救いを求めて願って書いたような気がします。
よくライブでも歌われる曲です。
銀行と土地ブローカーに生涯を捧げるような
悪夢のようなこの国の
飽食とエゴに満ちた豊かさの裏側で
痩せ細る南の大地
Woo 未来へのシュミレーション
Woo 破滅を示す時
鐘が鳴ってる 約束の地に
打ち上げられた罪を知る者に
鐘が鳴ってる 聖者のように
魂の声を聞く者に
闇を裂いて閃いてる やがて1999年
タブーだらけの自由の中で葬られてゆく
孤立した叫び声
自浄出来ぬシステムに真実は捻じ曲げられ
幻想だけ煽られてく
Woo プラスティックインフォメーション
Woo メディアを満たす時
鐘が鳴ってる 非武装の地を
争うことなく追われる者に
鐘が鳴ってる 天使のように
愛しい人を導く者に
見守るように遠く深く やがて1999年
鐘が鳴ってる 欲望の地で
誇りと理想に生きる者に
鐘が鳴ってる 詩人のように
傷付いた心いたわる者に
輝いてる清く強く やがて1999年
その他には
❝自分のエゴを守るために、いつも誰か敵を作らざるを得ない
でも結局、それは自分が作っているだけで
自分で自分を苦しめている❞
っということを歌っている曲
「SAME OLD ROCK'N ROLL」や
男と女は、どうしても友人ではいられず恋愛対象になってしまう。
想いを告げたら、そこで終わってしまうのが怖くて
良い関係をキープしていたいから、逆に臆病になってしまう。
そんな男の気持ちを歌った曲
「少年の心」
そして、戦力外通告を受けそうな瀬戸際の野球選手が
年老いて体が負傷しても、尚
❝ただ好きだから、やり続けたい❞という気持ちを
自分と重ね合わせながら
こういう野球選手がいてくれたら良いなと願って歌っている曲
「BASEBALL KID'S ROCK」があります。
※この「BASEBALL KID'S ROCK」については
ライブで歌ってくれる際に、省吾さんやバックバンドのメンバーで
野球をしているパフォーマンスもしてくれたりして
オーディエンスを楽しませてくれたりするんですよ(*^▽^*)b
そして、孤独感が伝わってくるような曲
「青の時間」や「サイドシートの影」は
聞いていると切ない気持ちになったりしてね。
当時の省吾さんの冷え冷えとした心情が
そこに秘められているのかと感じられたりしました。
全体的に、多面的な分野で救いを求めているように感じられてきます。

このアルバムに収録されている曲は…。
- MY OLD 50'S GUITAR
- BASEBALL KID'S ROCK
- 少年の心
- 青の時間
- サイドシートの影
- 恋は賭け事(ギャンブル)
- 夜は優し
- SAME OLD ROCK'N ROLL
- 太陽の下へ
- 詩人の鐘
- 夏の終わり
このアルバムの中で、私が好きな曲は…。
- MY OLD 50'S GUITAR
- BASEBALL KID'S ROCK
- 少年の心
- 青の時間
- サイドシートの影
- SAME OLD ROCK'N ROLL
- 太陽の下へ
- 詩人の鐘
- 夏の終わり
そして、このアルバムについて省吾さんは↓こう語っています。
前のアルバムから2年くらい経って、いよいよやらなくちゃってなったのが去年(1989年)の8月くらいだったんです。
どういうものをやるかは漠然としていてね。
あまりにも漠然としているから、どこかに籠もろうと。
籠るっていっても東京のど真ん中、夜景が見えるところじゃないとダメ、みたいな。
それでメロディーの切れ端くらい浮かんでこないかなと。
だけど、全く何も浮かんでこない。
その状態のまま、カナダ、アメリカに行ったんです。
向こうに行っても、ひたすら浮かんでくるメロディーは、オールマンブラザーズの「RUMBLIN' MAN」1曲だけなんです。
それは結果的にコップに水を注いでいた状態だったと思うんですけど。
基本的に自分がやりたかったことっていうのは、凄くトラッドなものですね。
ブルースであり、カントリーミュージックであり、ポップミュージックであるんだけど。
サウンドも、とにかくシンセサイザーはやめようと。
もう1回、ミュージシャンがプレイするところに帰りたいっていうのかな。
エモーショナルなもの、自分たちのテクニックの中でギリギリなものをやりたいなって、スタートしたんです。
思えば自分が「路地裏の少年」から、ずっと作ってきたのは、基本的には男が一人前になる、大人になろうとしている歌だと思う。
今回のアルバムは一人前になりかけている❝俺❞の音楽を聞いてくれと、ちゃんと言えるアルバムになったと思っているんです。
「浜田省吾事典」より
今回は、ウツ状態から抜け出そうとしながら
スタートしたアルバム制作だったようですけれど
「一人前になりかけている自分」っということにも気付いて
そんな状態の等身大の姿を
赤裸々に表したアルバムになってるように思えます。
前作と聞き比べてみると、一皮剥けたような印象を受けたりするのですが
少しテイストが逸脱していて、異質なアルバムだったような気もします。
そして、次なるアルバムでは
省吾さんらしいパワフルさが戻ってきて
ノリノリのロックや、壮大なバラードも生まれたりして
総合的にカッコイイ、アルバムになっています。
そのお話については、次に続きます(*^_^*)